
入浴
入浴で整える心と体の健康 「1日の疲れを癒す入浴習慣のススメ」
入浴と現代人のライフスタイルの変化
新型コロナの流行は、私たちの生活様式を大きく変えました。リモートワークや外出自粛が広がった2020年以降、自宅で過ごす時間が増え、健康への関心が高まった結果、入浴の価値も見直されました。「免疫力向上」や「ストレス軽減」といった効果が注目され、シャワーだけで済ませていた人たちも湯船に浸かる習慣を始めるケースが増えました。 しかし、2023年のコロナの分類変更に伴い、社会活動が再び活発化。忙しい日々が戻り、入浴の時間が削られ、シャワー派に戻る人も増えています。
入浴の健康効果と現代のニーズ
入浴には、温熱効果で血行を良くし、水圧で心臓を刺激し、浮力で筋肉をリラックスさせるなど、心身に嬉しい効果がたくさんあります。特に副交感神経を優位にするリラックス効果は、ストレス解消や睡眠の質向上に役立ちます。 現代人は忙しく、ストレスも多い中で、短い時間でも効果的にリフレッシュできる入浴が大きな助けになります。
最近では、アロマや音楽を取り入れた工夫も注目されており、手軽に楽しめる短時間入浴法の開発も期待されています。
忙しい日々でも、入浴を上手に取り入れることで心身を整えることが可能です。科学的根拠に基づいた新しい入浴方法の提案が進む中、入浴が健康で充実した生活を支える重要な存在であり続けるでしょう。

シャワーだけでは足りない「湯船に浸かる」価値
入浴の3大効果
湯船に浸かることで得られる3つの主な効果は、「浮力」「水圧」「温熱」です。これらはシャワーでは得られない、湯船ならではの健康効果を生み出します。
1.浮力
湯船に浸かると、アルキメデスの原理により体が軽く感じられます。人の体の比重は水と近いため、水中では水面に出ている部分だけの重さを感じるだけで済み、筋肉や関節への負担が軽減されます。
2. 水圧
お湯に浸かると、全身に水圧がかかり、特に深い部分では圧力が強くなります。この水圧により、お腹が押されて横隔膜が上に押し上げられます。その結果、肺の容量が約9%減少するとされますが、体の恒常性機能により呼吸数が増加し、肺の働きが維持されます。また、水圧が足元から心臓に向けて静脈血を押し上げるため、血液の循環がスムーズになり、心臓への血液の戻りが促進されます。この作用は、血行不良の解消やむくみの軽減にも繋がります。
3. 温熱
お湯の温かさは、外部からの熱が赤外線の形で体内に伝わり、体温を上昇させます。この過程では、タンパク質や遺伝子が媒介となり細胞や血管が温まります。また、温まった血管の内側(血管内皮細胞)から一酸化窒素(NO)が放出され、血管が柔らかくなり血流が良くなります。さらに、筋肉や関節をつなぐ腱(コラーゲン繊維)が柔らかくなることで、関節の可動域が広がり、体が動きやすくなります。このように、温熱効果はリラックスを促進し、心身の調子を整えるのに役立ちます。
湯船ならではの相乗効果
湯船ではこれらの効果が同時に働き、相乗効果を生み出します。たとえば、「水圧」と「温熱」による血行促進や、「浮力」と「温熱」による関節負荷の軽減などが挙げられます。これらの恩恵はシャワーだけでは得られず、湯船に浸かることによる特別な価値といえます。 短い時間でも湯船に浸かる習慣を取り入れることで、心身の健康を整える効果が期待できるでしょう。
具体的な入浴の健康効果
湯船に浸かることは、体温の上昇による血行促進や免疫機能の活性化だけでなく、睡眠の質向上や心のケアにも効果的です。忙しい日々の中でも、湯船に浸かる時間を確保することで、心身の健康を効率よく整えることができます。
湯船ならではの相乗効果
湯船に浸かることで得られる3つの主な効果は、「浮力」「水圧」「温熱」です。これらはシャワーでは得られない、湯船ならではの健康効果を生み出します。
1)血行促進
温かいお湯に浸かると、血管が柔らかくなり心拍数が上がり、血行が促進されます。血液は、体中に栄養や酸素を運び、免疫細胞やホルモンも循環させる重要な役割を担っています。そのため、血行が良くなることで冷えや凝りが軽減され、免疫バランスの維持にも役立ちます。一方で、血液循環が滞ると健康全般に悪影響を及ぼします。入浴は、この血液循環を整え、健康を支える大切な行為です。
2)免疫バランスの改善
入浴と免疫システムの関係ですが、体温と免疫システムの関係と言い換えることも出来ます。 湯につかると体温が上昇します。まず体温が上がると免疫細胞の一つである貪食細胞といわれて いるマクロファージが活性化します(*1)。マクロファージが活性化すると体に入った細菌をどんどん食べてくれて病気になり難くなります。また昨年、体温が36°Cより38°Cのマウスの方が免疫の バランスが整いウイルス性の肺炎の炎症を抑制することが分かりました(*2)。即ち体温が上がった方が免疫のバランスが整い、炎症を抑える効果が高まることがわかっています。お風呂に入ることは免疫を正常に保ち、病気にかかりにくい体づくりに貢献します。
3)良質な睡眠をサポート
入浴後、「疲れが取れる」と感じる理由は、良質な睡眠につながるからです。人は体温が下がると眠くなる生理的リズムを持っていますが、入浴はこの流れをサポートします。お湯に浸かることで体温が一時的に上がり、その後スムーズに下がることで入眠しやすくなるのです。また、血行が良くなることで栄養や酸素が体中に行き渡り、細胞の修復が進むため、睡眠の質も向上します。これにより、疲労回復や心身のリフレッシュが期待できます。
心への効果
湯船に浸かると「浮力」の効果で体が軽く感じられ、関節や筋肉への負担が減ります。特に、足や腰など負担のかかりやすい部分が楽になります。そもそもお湯につかると温まり、人は温まることで痛みは感じにくくなり(*3)、気持ちが和らぎます(*4)。 また、心地よい温度のお湯は副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。お湯の適温は個人差がありますが、「はぁ~気持ちがいい」と感じる温度を目安にすると良いでしょう。 さらに、お風呂は「自分だけの空間」であり、誰にも邪魔されない時間を過ごせます。この時間を利用して嫌なことを忘れたり、明日に向けて気持ちを整えたりと、マインドフルネスな体験を楽しむことができます。温かいお湯が体を和らげると同時に、心も穏やかにしてくれるのです。
入浴習慣を取り入れるために
理想的な入浴方法
入浴は「浮力」「水圧」「温熱」の効果を活かして、心身を整える時間です。ただし、人それぞれの体調やライフスタイルに合わせて、最適な方法を見つけることが大切です。以下に、効果的な入浴のポイントをご紹介します。
1. お湯の温度を調整する
お湯の温度は、リラックス効果を高める上で重要です。熱すぎると交感神経が優位になりリラックスできません。適温は個人差がありますが、以下の方法で見つけるのが良いでしょう。
1)まずは最初に40°Cでお湯を張る。
2)足を入れた時に「熱い」と感じたら1°C下げ、「ぬるい」と感じたら1°C上げる。
3)「気持ちいい、このままずっと浸かっていたい」と感じる温度が理想的な温度です。
2. 全身浴と半身浴の使い分け
入浴のスタイルも目的や体調に応じて選びましょう。
◼︎全身浴
肩までしっかりお湯に浸かる方法です。足やお腹に強い水圧がかかり、血流が促進されます。
特に疲労回復や血行促進を目的とする場合に効果的です。
◼半身浴
みぞおちまでお湯に浸かる方法です。全身浴よりも水圧が少ないため、心臓や肺への負担が軽減されます。
体力が落ちている時や、心肺機能に不安がある場合に適しています。
3. 入浴時間を工夫する
入浴時間も健康効果に大きく影響します。
◼短時間の入浴(6~7分)
皮膚温がピークに達するため、軽い疲れやリフレッシュ目的には最適です。特にデスクワークが中心の日には、この程度で十分効果が得られます。
◼長めの入浴(15分程度)
筋肉の温度がピークに達し、血流が筋肉までしっかり届く時間です。運動後や立ち仕事が多かった日は、筋肉疲労を軽減するために15分程度浸かると良いでしょう。 ただし、長時間の入浴は注意が必要です。皮脂が失われて肌が乾燥しやすくなるため、入浴後のスキンケアが必要です。また、脱水のリスクを避けるため、入浴前後にしっかり水分補給を行いましょう。
4. 自分の体調に合わせる
その日の体調や目的に合わせて湯温、深さ、時間を調整しましょう。
◼疲れが軽い日は短時間でさっぱりと。
◼筋肉疲労がある日は15分以上しっかり浸かる。
◼体力が落ちている日は半身浴で無理をせず。
5. バスタイムを楽しむ工夫

入浴はリラックスするための大切な時間です。アロマオイルを入れたり、好きな音楽を流したりと、自分なりの楽しみ方を加えてみましょう。お湯の温度や浸かる時間を工夫することで、入浴は「なりたい自分」を叶える特別なひとときになります。 入浴は心身を整える最適な習慣です。湯温、時間、入浴スタイルを工夫して、自分の体調に合ったバスタイムを楽しみましょう。そして、入浴後は適切なスキンケアと水分補給を忘れずに行うことで、その効果をさらに高められます。
バスタイムをさらに楽しむために入浴剤を取り入れてみませんか。
健美薬湯の「JIKKO」は、生薬薬湯として全国の銭湯で長年愛用されてきた「温浴素じっこう」を家庭用に改良した入浴剤で、日常の癒しに最適です。この入浴剤には、生薬「川芎(センキュウ)」が配合されており、血行促進や冷え性、肩こり、疲労回復に効果的です。さらに、温泉成分にも含まれる天然ミネラルが体の芯までしっかり温め、湯冷めしにくいのが特徴です。「JIKKO」を使えば、自宅にいながら銭湯や温泉のような気分を楽しむことができます。個包装タイプなので、忙しい日々の中でも手軽に使え、毎日の習慣に取り入れやすいのも魅力です。お気に入りの入浴剤で、特別なリラックスタイムを演出し、日々の疲れを癒してみてはいかがでしょうか。
まとめ
湯船に浸かると「浮力」の効果で体が軽く感じられ、関節や筋肉への負担が減ります。特に、足や腰など負担のかかりやすい部分が楽になります。そもそもお湯につかると温まり、人は温まることで痛みは感じにくくなり、気持ちが和らぎます。 また、心地よい温度のお湯は副交感神経を優位にし、リラックス効果をもたらします。お湯の適温は個人差がありますが、「はぁ~気持ちがいい」と感じる温度を目安にすると良いでしょう。 さらに、お風呂は「自分だけの空間」であり、誰にも邪魔されない時間を過ごせます。この時間を利用して嫌なことを忘れたり、明日に向けて気持ちを整えたりと、マインドフルネスな体験を楽しむことができます。温かいお湯が体を和らげると同時に、心も穏やかにしてくれるのです。
- 参考文献 -
(1)Kashio M.,Sokabe T.,Shintaku K.,Uematsu T.,Fukuta N.,Kobayashi N.,Mori Y.,Tominaga M. (2012) Redox signal-mediated sensitization of transient receptor potential melastatin 2 (trpm2) to temperature affects macrophage functions. Proc Natl Acad Sci U S A, 109(17), 6745-6750.
(2)Nagai M.,Moriyama M.,Ishii C.,Mori H.,Watanabe H.,Nakahara T.,Yamada T.,Ishikawa D., Ishikawa T.,Hirayama A.,Kimura I.,Nagahara A.,Naito T.,Fukuda S.,Ichinohe T. (2023) High body temperature increases gut microbiota-dependent host resistance to influenza a virus and sars-cov-2 infection. Nat Commun, 14(1), 3863.
(3)岩﨑 真弓,野村 志保子 (2002) 279)局所温罨法によるリラクゼーション効果の検討
-温罨法と足浴が身体に及ぼす影響の比較検討より-. 日本看護研究学会雑誌, 25(3), 3_376-373_376.
(4)大橋 久美子,縄 秀志,佐居 由美,矢野 理香,樋勝 彩子,櫻井 利江 (2017) 国内における「気持ちよさ」 をもたらす看護ケアに関する統合的文献レビュー. 日本看護技術学会誌, 16, 41-50

日本薬科大学 医療ビジネス薬学科 特任教授/スポーツ健康科学博士/温泉入浴指導員
石川 泰弘
2006年から「お風呂博士」として(株)バスクリンで入浴剤のPR活動を行い、2021年より現職。専門は入浴と睡眠を活用したリカバリーで、運動生理学や美容についても研究・指導を行う。トップアスリートへの入浴指導やサポート経験が豊富で、メディアや講演を通じて入浴と健康の重要性を発信している。
入浴習慣に銭湯の温もりを
入浴習慣をはじめるなら、毎日でも飽きない天然の香りに生薬とミネラルの温浴効果で心と体を整えて、まるで銭湯で温もりを自宅で楽しめる入浴剤。
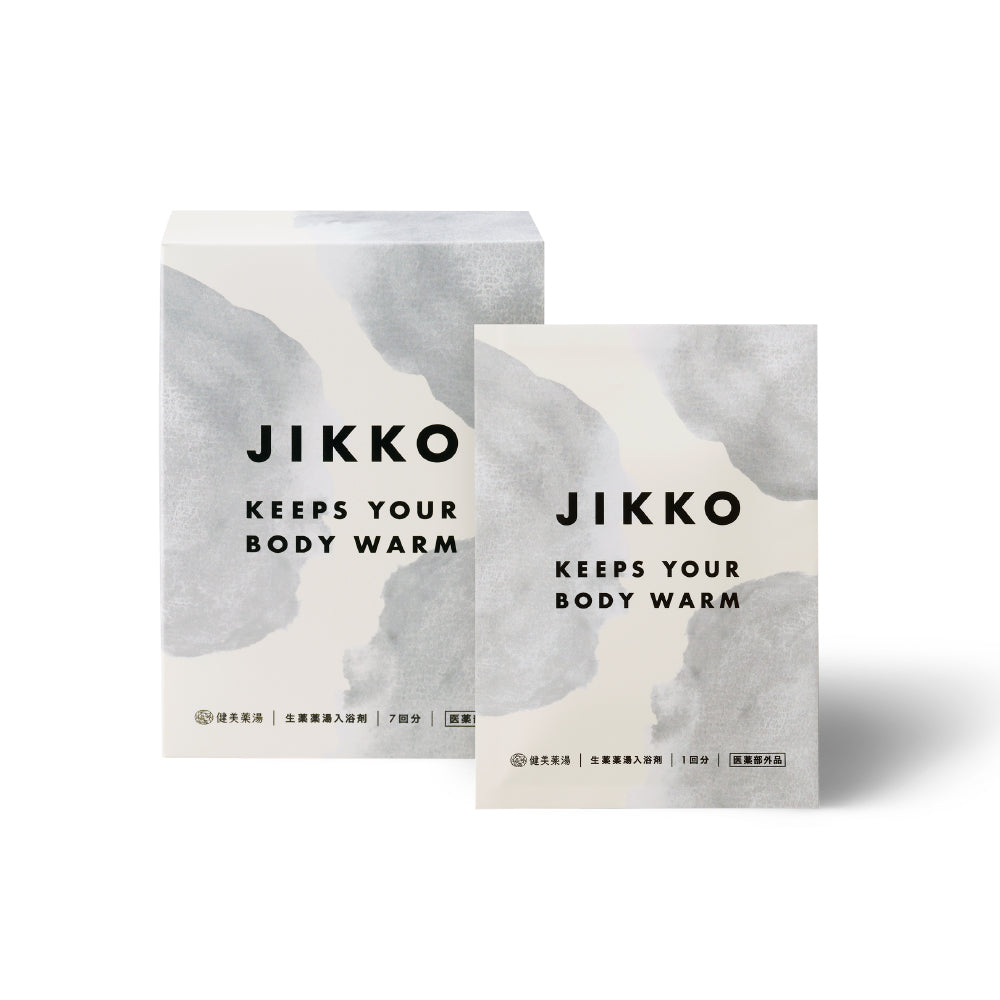
JIKKO 生薬薬湯入浴剤
ずっとポカポカ温かい、巡りの良いカラダへ導く生薬薬湯入浴剤。17種の効能・効果でカラダを温めます。

