
温泉
温泉の不思議 「なぜ温泉に入ると体が芯から温まるのか?」
はじめに:温泉の魅力
日本は「温泉大国」と呼ばれるほど、温泉が豊富な国です。環境省の調査によると、全国に約28,000もの源泉があり、温泉地は約3,000箇所にのぼります。年間利用者数は延べ1億1千万人と、日本の人口とほぼ同じ規模です。つまり、多くの日本人が毎年温泉を訪れていることが分かりますね。
温泉は古くから日本人の生活に深く根付いてきました。例えば、古事記では少彦名命(すくなひこな)が温泉で命を取り戻したという記述がありますし、日本書紀には聖徳太子や舒明天皇(じょめいてんのう)が道後温泉を訪れたと記されています。自然の恵みである温泉が、昔も今も変わらず人々に癒しを与え続けているのです。
温泉で体が温まる科学的な理由
温泉の出来方
温泉に浸かると体が芯から温まり、心も癒されますね。でも、温泉がどのようにしてできるかご存じですか?温泉の生成には、以下の3つの仕組みがあります。
1.火山性温泉
日本は環太平洋火山地帯に位置しており、地下に浅いマグマ溜まりがあります。このマグマの熱で地下水が温められ、断層や地表の裂け目から湧き出すのが火山性温泉です。マグマは地球の中心にあり、その温度は650~1300°Cに達するとされています。
2. 非火山性温泉
地球内部の熱(地熱)によって地下水が温められることで湧き出す温泉です。地表から100m深くなるごとに約3°C温度が上がるため、地下深くの水が熱せられて温泉になります。
3. 化石海水温泉
過去の地殻変動で地中に閉じ込められた古代の海水が地熱で温められ、断層などから湧き出してくるものです。このタイプの温泉はミネラルを多く含み、独特の成分を持っています。
温泉の定義と管理
温泉は1948年(昭和23年)に制定された温泉法で定義されています。以下のいずれかの条件を満たすものが温泉と呼ばれます。
- 湧出時の水温が25°C以上
- 特定の成分が規定の量以上含まれている
例えば、地表が0°Cでも地下1,000mの深さでは水温が約30°Cになるため、掘削によって温泉を得ることが可能です。最近では掘削技術が進み、3,000m程度の深さまで掘ることも可能になり、東京丸の内のような都市部でも温泉が湧き出る例があります。
ただし、温泉を掘るには行政の許可が必要です。地盤への影響を考慮する必要があるほか、掘削やポンプ設置には約1億円もの費用がかかると言われています。そのため、資金力も重要です。
温泉分析書の掲示
湧き出た温泉は、成分や性質を調査し行政に届け出て認可を受ける必要があります。この結果を記載したのが温泉分析書です。この分析書は「温泉の成績表」とも呼ばれ、次のような情報が記載されています。
- 含有成分やその量
- 泉質の分類
- 湧出時の温度や浴槽の温度
- 浸透圧や液性(酸性・アルカリ性など)
温泉分析書は掲示が義務付けられており、10年ごとに再調査と更新が行われます。この温泉分析書を見るだけで、温泉の特徴をある程度把握することができるため、訪れた温泉地でぜひチェックしてみてください。

温泉成分から泉質と人体への効果
温泉には多様な成分やガスが含まれており、その成分の種類や量によって泉質が決まります。ただし、温泉は自然の恵みであり、成分量は日々微妙に変化することがあります。このため、一定の目安として温泉法で定められた10種類の泉質が掲示されています。それぞれの泉質とその人体への効果について詳しく説明します。
単純泉
単純泉は指定成分の量が基準値以下ですが、湧出時の温度が25°C以上ある温泉です。比較的日本には多いと言われています。成分量が少ないため、肌への刺激は少なく比較的入りやすい温泉と言えるでしょう。
塩化物泉
塩化物泉は読んで字の如く、塩(塩化ナトリウム)が多く含まれている温泉です。火山活動や地熱で地下水が熱せられ、岩石から塩分も溶け出すことがあったりまた、太古の昔、日本は海に沈んでいた時期があり、その当時の海水が地中に閉じ込められていたりもします。化石海水と言われるものですが、長い年月をかけて塩分濃度を高めて食塩泉となっている可能性もあります。もちろん日本は海にかこまれているので、この海水が地下に染み込んで塩分濃度を上げる可能性もあります。このようにできた食塩泉の効果は入浴中の血流も高めますが主には肌に分着してナトリウムが熱放散を防いで保温効果を高めます1。
炭酸水素塩泉
炭酸水素塩泉は重曹(炭酸水素ナトリウム)を多く含む温泉で、「美人の湯」、「美肌の湯」と言われる温泉です。炭酸水素ナトリウムが多く含まれるとお湯の液性はアルカリ性に傾きます。人の皮膚は弱酸性で、バリア機能として皮脂があり、皮脂も弱酸性を保っています。アルカリ性のお湯に肌を入れると、お湯に含まれるアルカリ成分が皮脂と反応して、皮脂は分解されて脂肪酸とグリセリンに変わります。分解された脂肪酸は、お湯中のナトリウムイオンやカリウムイオンと結合し、脂肪酸塩(石鹸)をつくります。このつくられた脂肪酸塩に、水と油を混ぜ合わせると乳化作用がおこり、皮脂や汚れが乳化されて、お湯に浮きやすくなり、ぬるぬるとした感触を生じます。
お湯につかっているだけで、皮脂がとれて汚れが浮き、軽く擦るだけで汚れが取れて、綺麗な肌になります。このような理由から「美人の湯」「美肌の湯」と言われるのです。決して成分が肌に入り潤うわけではありません。皮脂がアルカリ性の水と反応して汚れと浮き上がらせ、汚れと一緒に流れるので入浴後の乾燥は進みます。お肌は皮脂が取れて綺麗になるのですのが入浴後は乳液やクリームでしっかりとスキンケアをする必要があります。
硫酸塩泉
硫酸塩泉には硫酸ナトリウムを主な成分とする芒硝泉と硫酸マグネシウムを主成分とする正苦味泉とカルシウムを主成分とする石膏泉があります。芒硝泉と正苦味泉の主成分である硫酸ナトリウムと硫酸マグネシウムは風呂釜への影響も少ないので入浴剤の主成分となることもある。そして石膏泉はカルシウムが肌に付着し肌をサラサラにします。肌をカルシウムでコーティングすることから傷の湯と言われることもあります。
二酸化炭素泉
二酸化炭素泉は炭酸ガスを多く含む温泉です。炭酸ガスはお湯に溶け込んで経皮吸収(けいひきゅうしゅう)されます。経皮吸収とは、皮膚を通じて物質が体内に吸収されることを言います。肌から入った炭酸ガスは皮膚の血管について血管の硬さをコントロールしている血管平滑筋という筋肉を弛緩します。緩めてくれます。血管そのものが柔らかくなるということです。お湯に体をいれると水圧がかかり心拍数が上がるので血液は多く送り出されます2。血管が柔らかくなっているので自ずと血流量が増加します。このようなメカニズムで血行促進するということになります。温かい血液が多く全身を巡るので体が温まります。
硫黄泉
硫黄泉には硫化水素ガスが含まれています。硫化水素ガスも炭酸ガスと同じような働きを示します。お湯に溶け込んだ硫化水素ガスが経皮吸収され血管平滑筋を弛緩し血管そのものを柔らかくします。そして心拍数の増加により血行促進となります。
また、温泉に含まれる硫黄は空気に触れるとコロイドをつくります。コロイドとはとても小さな粒子が液体の中に均一に分散している状態のことで、この粒子のサイズは通常は1ナノメートルから1マイクロメートルの大きさとなります。
このコロイドはどのように出来るかというと、硫黄が空気中の酸素に触れると反応して酸化硫黄という物質になります。この酸化硫黄は水と反応して、硫酸という酸性の物質になり、液性としても酸性に少し傾く傾向があります。この硫酸が水の中に分散することで、硫酸の微粒子がコロイドとなります。硫酸は水に溶けると、非常に多くの熱を出すため、周りの水分子を激しく振動させます。この振動によって、硫酸の微粒子は互いにくっつきにくくなり、水の中に安定して分散することができます。
そしてこのコロイドに光が反射して温泉の色をつくります。コロイド粒子が大きいと白く見え、小さいと青く見える、その中間が緑と言われています。牛乳が白く見えるのもコロイドに反射した光が目に入り白く見えるということです。
一方硫黄と銀が結びつくことで「硫化銀」という黒く変色してしまいます。銀製品を身につけて硫黄泉に入らないようにしましょう。
含鉄泉
含鉄泉には鉄分が多く含まれています。鉄は空気中の酸素に触れると酸化します。錆びると言った方がわかりやすいですね。お湯の色は赤茶色くなり、鉄サビ独特の匂いがします。実は鉄の熱伝導率は高いため、他の泉質の温泉と比較して、より早く体の芯まで温まる可能性はあります。また、鉄が酸化するときには熱を発生させるので、酸素と触れやすい表面の方が酸化しやすいので、わずかでしょうが湯温は上昇する可能性も考えられます。
酸性泉
酸性泉は主に硫酸や塩酸などが水に溶け込むことで、温泉の水が酸性になります。お湯が酸性に傾くと殺菌効果が高まります。何故かというと、酸性の環境では、水素イオン濃度が高くなり、細胞膜が損傷したり、酵素の働きが鈍くなったりすることで、微生物が増殖するのを抑えることができます。もちろん酸性の環境でも増殖してしまう細菌もいますが。しかし、多くの細菌は酸性の環境下に適応でないので、殺菌力が強いと言われているということです。一方細菌の増殖を防ぐということは、その分肌への刺激は強くなりますので、注意が必要となります。
放射能泉
放射能泉には土壌や岩石に含まれるラジウムがアルファ壊変して生成される放射性のラドンという希ガスが溶け込んでいます。このガスからα線という放射線がでます。この放射能泉につかると被爆するのですが、浸透力が弱いので皮膚表面で吸収され体の深部まで入ってくることはありません。お湯から出るラドンガスを吸入することで、肺がα線に被曝します。ラドンガスは、お湯だけでなく、空気中にも存在するため、浴場全体がラドンガスに包まれているような状態になります。また、ラドンは半減期が短い元素で、時間が経つにつれて放射能が弱まっていくことと、そもそも放射線量が少ないので人体に悪影響を与えることはありません。ラドンのα線は、人体に当たるとわずかな熱を発するので、この熱が温泉での温熱効果を高めるのです。
含ヨウ素泉
含ヨウ素泉には、よう化物イオンが含まれています。2014年に新泉質となりました。ヨウ素は、海藻などに多く含まれるミネラルで、私たちの体にとっては必須の栄養素の一つです。また、強力な殺菌作用を持っており、皮膚の雑菌を殺菌する効果が期待できます。お湯の色もヨウ素と空気中の酸素とが反応してヨウ素が遊離し時間が経つにつれ黄色く変色してきます。ヨードチンキをイメージしてもらえると良いと思います。特有のにおいでまさにヨードチンキを感じる匂いです。
これらの泉質を理解し、自分の体調や目的に合った温泉を選ぶことで、温泉の効果をより一層引き出すことができます。温泉はまさに自然が与えてくれる癒しの宝庫と言えるでしょう。
温泉を利用する際の注意点
温泉の禁忌
これまで、泉質の違いや人に与える効果について説明しました。実は温泉の成分量は市販の入浴剤とは比べ物にならない程多く含まれています。それだけ人の体に与える影響は強くなります。ですから体調やその人の病気や状態によっては温泉に入ると体調が悪化してしまうという理由から温泉入浴をしないように定めたものがあります。それが「禁忌」と言われるものです。
具体的には以下の症状のある人は温泉入浴をしないようにしてください。
- 急性疾患(特に熱のある場合)の人
- 活動性の結核に感染している人
- 悪性腫瘍に罹患している人
- 重い心臓病の人
- 呼吸不全の人
- 腎不全
- 出血性疾患の人
- 高度の貧血の人
また、硫黄泉と酸性泉は肌への刺激が強いため、皮膚または粘膜が敏感な人、そして高齢者皮膚疾患に罹患している人は禁忌とされています。
入浴前のリラックス
温泉旅行で長旅を終えた後、すぐに熱い湯に入るのは避けましょう。

温泉地で暮らしている人は日々が日常ですが、多くの人が温泉地に足を運ぶのは日常生活から違う空間に身を置きたいという気持ちがあります。そのため様々な交通手段を利用し、多少遠くても足を運びます。そしていよいよ温泉地に入り、予約した宿でチェックイン。
気持ちは「さあ、まずは温泉につかろう」とテンションがあがります。その時、自分の自律神経はどうなっているのでしょう。まず、長い移動距離と時間で体は疲れ交換神経も優位となっているでしょう。
そこで目の前に現れた目的の宿。テンションはさらに上がります。交感神経は更にあがってきます。そして部屋に荷物を置きまずは温泉だとお風呂に足を運びお湯の温度も気にせず温泉につかります。熱ければ交感神経が更に上がり、いつ入浴事故を起こしてもおかしくないという状況です。
振り返ってみると、宿にチェックインの後は部屋に入ります。
そこにはお茶とお茶菓子が用意されています。きっと多くの人はその意味を意識もしないでしょう。
しかし、そこに置いてあるお茶とお茶菓子にはちゃんと意味があります。部屋に入った時にお茶を飲みお茶菓子を食べると心が落ち着きます。すると高まっていた交感神経も抑えられて通常にもどります。そのような状態で温泉に入ると入浴事故を起こすリスクが軽減されます。お茶とお茶菓子はすでに宿泊料にふくまれているので追加料金も払う必要もありません。また、お茶菓子も美味しかったらお土産に購入して、自宅で食べれば良い思い出となります。折角の温泉旅行で入浴事故を起こしてしまわないようにお茶とお茶菓子を楽しみましょう。
温泉で得られる健康効果
温泉には家庭での入浴で得られる健康効果に加え、成分の効果、そして日常生活とは異なる空間に身を置くことで心がリフレッシュされ、その状態が身体を良い状況に導く転地効果があります。転地効果は温泉でしか味わえない効果です。
温泉とウェルネスツーリズム
近年、温泉地では、単に温泉に入浴するだけでなく、心身のリラックスや健康増進を目的とした「ウェルネスツーリズム」が注目されています。具体的にはウォーキングをしながら、その土地の歴史や食文化触れる、またヨガや瞑想、そして森林浴や川遊びといった自然体験などを取り入れ、温泉の持つ体への良い影響や癒やしの力と組み合わせて、より深いレベルでの健康と幸福を求めるものです。実際に別府温泉で行われた4泊5日間のプログラムではストレスホルモンであるコルチゾールが減少したとの報告もあります3。そして温泉地に人が訪れるウェルネスツーリズムは、個人だけでなく、地域社会にも様々な良い影響をもたらします。
温泉のパワーを楽しもう
日常の忙しさから解放され、心身ともにリフレッシュしたいと思った時、多くの人が温泉を思い浮かべるのではないでしょうか。温泉は、古くから人々に癒しを与えてきた日本の宝です。そこにはお湯による温熱や地面から湧き上がる時に含まれる成分のこうか、そして非日常という転地効果あります。まさに体と心、人間そのものを良い方向に導く自然の力、天からの贈り物です。
そんな温泉を更に良いものにするには体調や悩みに合わせて、自分に合った泉質の温泉を選びましょう。また、温泉地には、温泉だけでなく、その土地の歴史ある建物や自然豊かな場所など、見どころがたくさんあります。また、その土地の郷土料理があり、地元の食材を使った料理を味わうことで、旅行の思い出がさらに深まります。単に温泉だけでなく、周辺観光も合わせて楽しむことで、より充実した温泉地の活用が出来ます。
温泉は、単に体を温めるだけでなく、心身のリフレッシュや健康増進に役立つ素晴らしいものです。そこに自然環境や歴史、食文化を満期することで、温泉の持つパワーを最大限に引き出せ、豊かな時間を過ごせます。
是非温泉をトータルで楽しんでください。
- 参考文献 -
1.堀切 豊, 下堂園 恵, 王 小, et al. 高濃度塩類泉 (Na, Ca, Mg塩化物, 硫酸塩) 入浴の深部体温と循環動態への効果. 日本温泉気候物理医学会雑誌. 2000;63(4):181-186. doi:10.11390/onki1962.63.181
2. MAEDA M, NAGASAWA H, SHIMIZU S, YORIZUMI K, TANAKA K. The Concentration of Artificial CO2 Warm Water Bathing and the Skin Blood Flow. The journal of Balneology, Climatology and Physical Medicine 2003:1980-1984.
3. 前田 豊, 牧野 直, 堀内 孝. 温泉地ツアーによるストレス解消と血清コルチゾール値について. 日本温泉気候物理医学会雑誌. 2019;82(2):70-77. doi:10.11390/onki.2320

日本薬科大学 医療ビジネス薬学科 特任教授/スポーツ健康科学博士/温泉入浴指導員
石川 泰弘
2006年から「お風呂博士」として(株)バスクリンで入浴剤のPR活動を行い、2021年より現職。専門は入浴と睡眠を活用したリカバリーで、運動生理学や美容についても研究・指導を行う。トップアスリートへの入浴指導やサポート経験が豊富で、メディアや講演を通じて入浴と健康の重要性を発信している。
自宅でも温泉効果を楽しめる!健美薬湯の「JIKKO」
温泉旅行に行きたくても、忙しくてなかなか時間が取れない......そんな方にぴったりなのが、**健美薬湯の「JIKKO」**です。全国の銭湯で40年以上愛され続けてきた薬用入浴剤「温浴素じっこう」を家庭用に改良したこの入浴剤は、自宅のお風呂で温泉のような癒し効果を楽しめるアイテムです。
「JIKKO」は、冷え症、肩こり、腰痛、神経痛、リウマチ、疲労回復など、17種類の効能が期待できる医薬部外品。配合されている生薬「川芎(センキュウ)」は、微粉末でまるごと使用され、さらに温泉にも含まれるミネラルと組み合わせることで、温浴効果を高めています。
また、「JIKKO」は合成香料、防腐剤、着色料、アルコールを一切使用しておらず、天然の生薬の香りが心地よいリラックスを誘います。まるで温泉地で癒されているような感覚が、自宅のお風呂で手軽に味わえるのが魅力です。
忙しい日常の中でも、自宅で温泉気分を味わいながら、心も体もほぐしてみませんか?温泉旅行気分を感じられる「JIKKO」、ぜひ一度試してみてください。
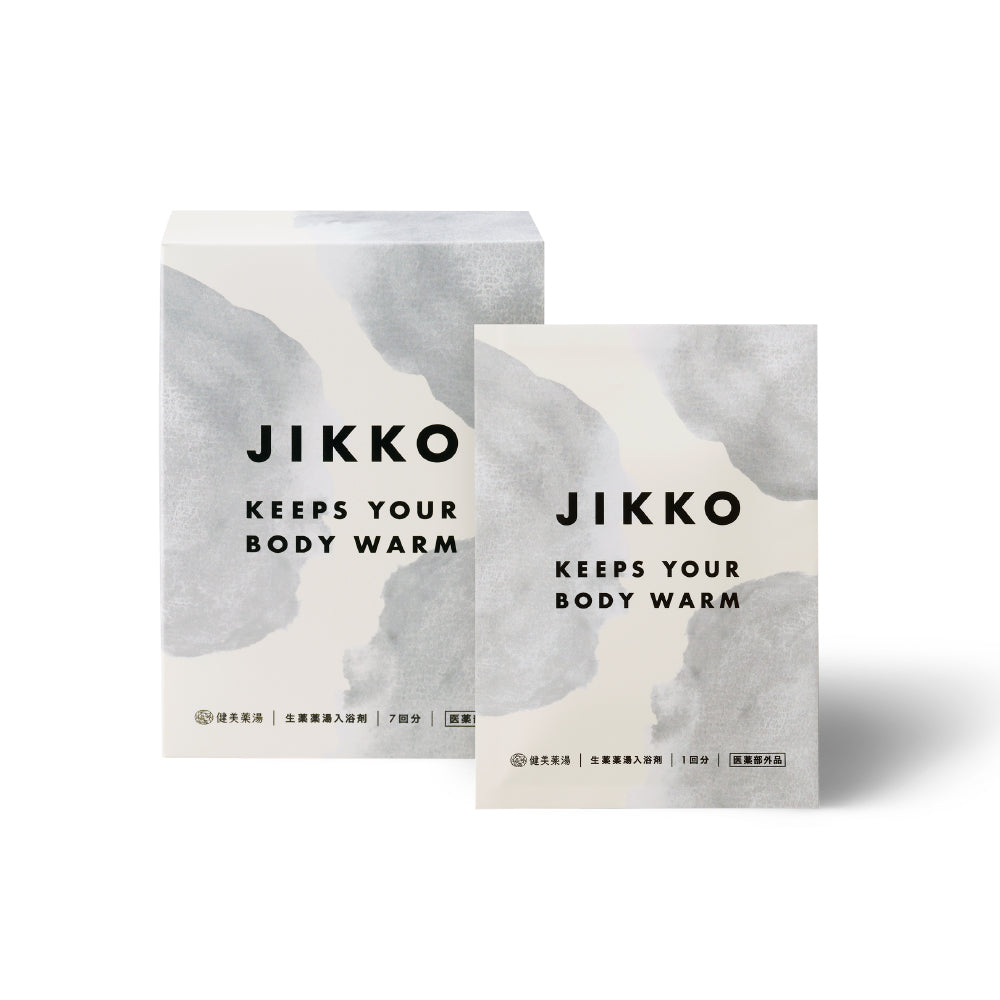
JIKKO 生薬薬湯入浴剤
ずっとポカポカ温かい、巡りの良いカラダへ導く生薬薬湯入浴剤。17種の効能・効果でカラダを温めます。
